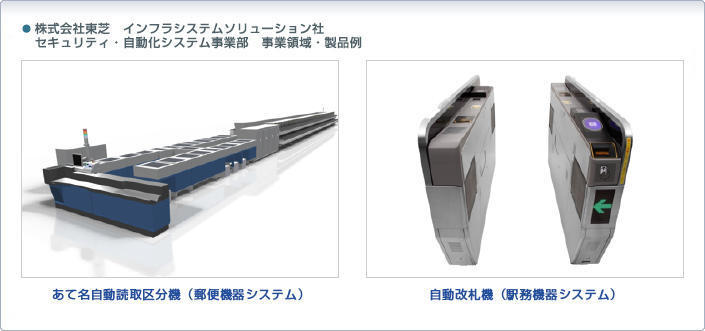手間の掛かる仕組みは定着しない
主務 松本敏紀 氏
“即戦力を求められる若手は情報収集の要領の良さを鍛錬するための期間が少ない。Knowledge Explorerなら効率的な情報収集の術を提供できると思っています。”
ビジネスユニットを横断した情報共有を
このような中で、品質保証部門を中心としてビジネスユニットを横断した情報共有の仕組みを強化したいという要望が出てきました。
主務 野呂文秀 氏
“「今までに無い仕組みだ」というのが率直な感想です。「発想支援」というイメージを持ちました。「人手を使わずに何かやろう!」というコンセプトは他にはありませんでしたね。”
少ない負担で、かつ直観的な仕組みを求めて
過去にも色々な製品を検討してきましたが、管理者と利用者の双方の負担が大きいものが多く、検討段階で「これは難しいな」と感じる事が多々ありました。社内に定着させるには簡単に情報を探せる仕組みでないといけません。
社内には既に整備されているデータベースシステムや、文書管理システムがあり、文書検索の仕組みもありましたが、検索のシステム負荷が高く、検索を掛けると、対象のデータベースや文書管理システムの動作が重くなり、利用しにくいケースもありました。また、文書管理システムは機能が多すぎて、現場の社員から直観的に利用できないという意見も出ていました。一見簡単に利用できそうな、これらの既存社内システムにすら沢山の課題や意見が存在しており、人的・システム的に負荷をかけないで、かつ直観的に社内情報を横断検索できる仕組みが必要だろうという思いが強くなっていきました。
人手をかけないというコンセプトは、他社にはなかった
仮に、設計仕様の検討という利用用途を考えた場合、過去モデルのデザインレビューで指摘されていた内容が、今回の設計では考慮されておらず、試作段階でその検討不足が発見されるというケースがあり得えます。もちろん量産に入る前の段階ですので、途中で検討不足に気付き、対策を施しますから最終的な品質は守られます。ただ、途中での手戻りが発生していますので、できればこれを無くしたいわけです。つまり、未然防止を行いたいのです。例えば、当事業所では静電気防止策がどの製品でも必要になってきますが、担当者がこの防止策や過去の失敗例、不具合事例をきちんと把握する事は、その労力を考えると簡単ではありません。単純な情報検索の仕組みでは、人やチームによってバラツキが発生してしまいますので、これも防止したいと思っていました。