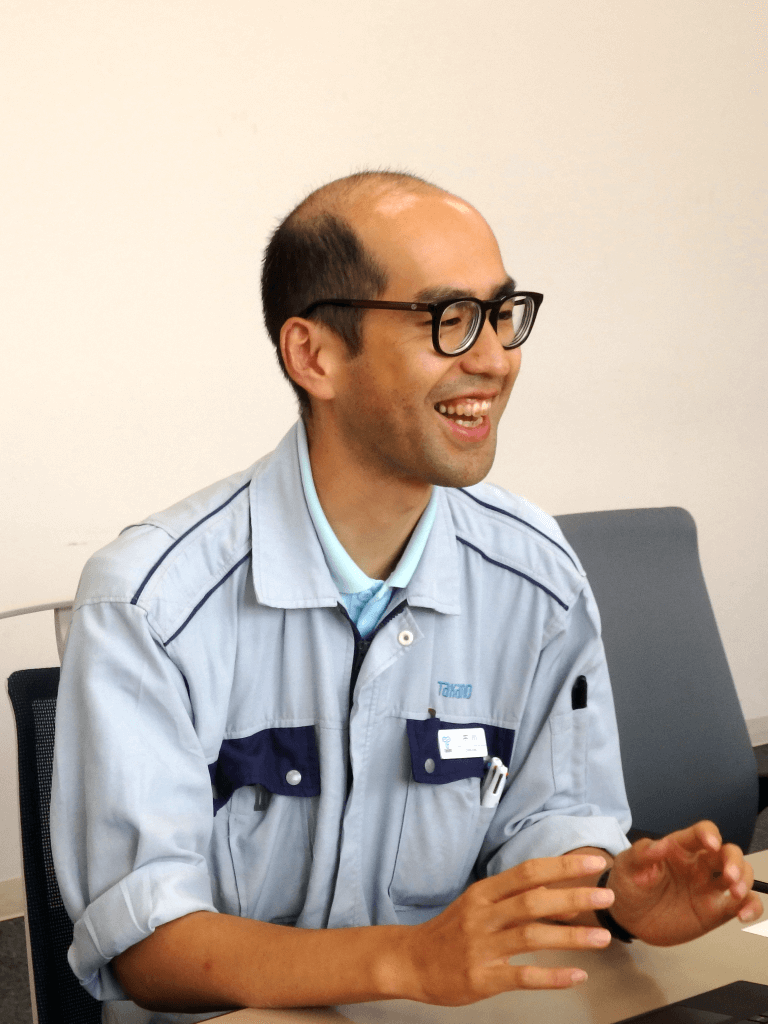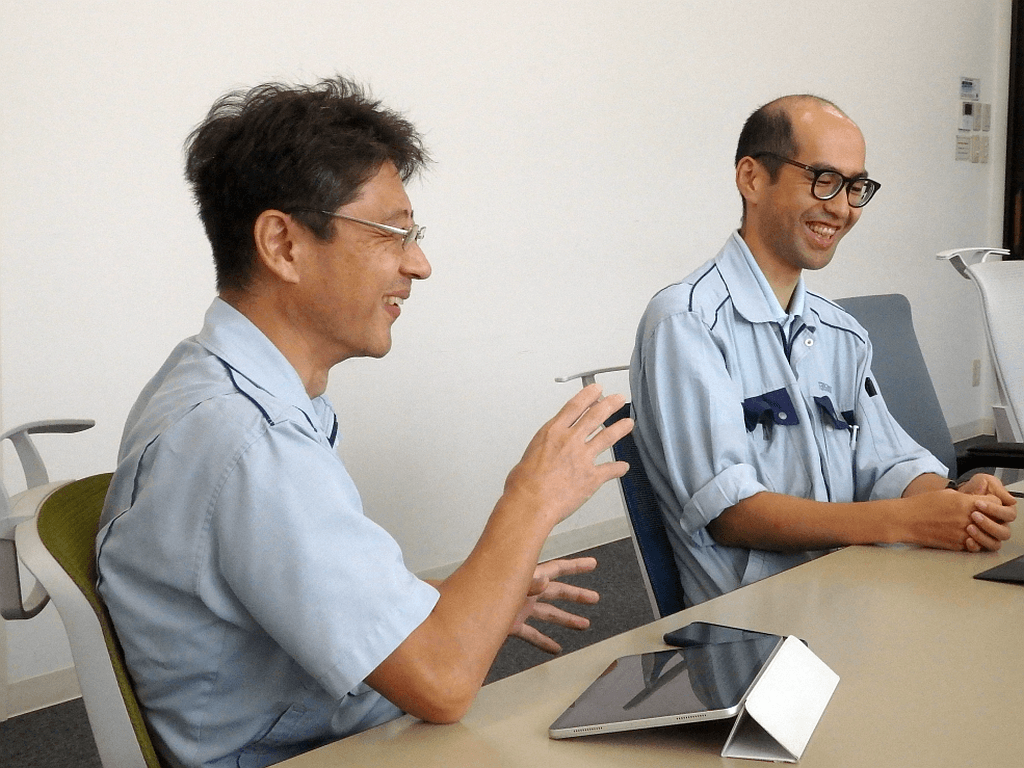オフィス家具メーカーのナレッジ活用事例
タカノ株式会社
タカノは、1941年の創業以来培ってきた固有のばね技術による、オフィス家具、エクステリア製品の製造をはじめ、産学共同研究によって開発した原子間力顕微鏡や液晶パネルの検査装置などのエレクトロニクス製品、高齢化でニーズの高まる健康福祉関連製品など、多彩な事業を展開する総合メーカーである。特に、オフィス家具の製造は、事業の大きな柱のひとつであり、大手オフィス家具メーカーのオフィスチェアをOEM生産している。
そんな同社では、構造解析データなどの設計情報、ユーザー問い合わせ情報、過去トラブルなどの共有化が思うように進まず、知識やノウハウの属人化がなかなか解消されない状況に危機感を抱いていた。
今回、オフィス家具事業を担当する、同社のファニチャー部門開発部のお二方にインタビューを行い、Knowledge Explorer導入の狙いや今後の期待について話を伺った。
お客様の企業プロフィール
- 会社名
- タカノ株式会社
- 本社
- 長野県上伊那郡宮田村137
- 社員数
- 480名(2018年3月31日現在)
- 事業内容
事務用椅子、その他椅子等のオフィス家具、ばね、エクステリア製品、エレクトロニクス関連製品、健康福祉機器の製造ならびに販売
お話を伺った方
-
ファニチャー部門 開発部 部長
堀木 敏幸 様
-
ファニチャー部門 開発部
ソリューション開発課 先行開発係 係長市川 智昭 様
2019年09月18日
採用いただいたソリューション

AI実装フルオート型
ナレッジ活用ソリューション
新しい価値の創造を阻む、開発業務の「属人化」
タカノも設計者CAEを推進する企業の一つであり、属人化を防ぐために、早いうちからノウハウが共有できる環境構築に取り組んできた。同社 ファニチャー部門 開発部 ソリューション開発課 先行開発係 係長の市川氏は次のように語った。
「当社では構造解析データベースを構築し、解析モデルや結果などのデータを蓄積し、共有できるようにしています。昔は私一人が解析担当者だったので、少しずつでも確実にデータを蓄積していくことができました。しかし、設計者CAEを推進し、各設計者が解析業務を担当するようになると、データを登録しない人が出てくるなど状況が変わってきました。」
先行開発係 市川智昭 様
「データを登録しないだけでなく、そもそもデータベースを参照することなく、独自路線で業務を行う人が目立ってきました。我々、開発部門は、設計者一人ひとりが新しい価値をお客様に提供する、いわば付加価値志向で開発していくことを使命としています。その使命を達成するには、各設計者の個人プレイに依存するやり方だと限界があります。たくさんの知識や情報を互いに共有し、それを活用していかないと、新しい価値を生み出していくのが難しい時代です。」
こうした状況を解決すべく、同社では新たな情報共有の仕組みを構築するため、市川氏を中心としたデータベース刷新プロジェクトを立ち上げることとなった。
「現在のデータベースはだいぶ前に構築したということもあり、改修できる内容に限界を感じていました。また、もう少し使いやすく、現代風にアレンジしたいという思いもありました。そこで、データベースを刷新する方向で検討を進めようという方針が決まり、市川の持ってきた答えが Knowledge Explorer でした。」(堀木氏)
分かりやすく探しやすい仕組みにより、情報共有を促進
また、同製品は情報をデータベース化して共有する製品とは異なり、管理対象とする情報のテーブル定義や、データ登録手順をユーザーに周知徹底させることなく、すぐに利用を開始できるのも大きな特長だ。
こうして、タカノのKnowledge Explorer導入が決定し、同社内でテスト運用が2カ月ほど実施された。テスト運用の準備にあたり苦労した点について市川氏に尋ねたところ、特に大きなトラブルはなく進められたという。
その後、2019年8月、同社ファニチャー部門開発部にて正式に運用が開始された。現在、40万近くの文書を対象に、総勢30名ほどのメンバーに利用されている。効果の程が問われるのはこれからだが、市川氏は次のように語った。
「今までのデータベースよりも使い方が分かりやすく、また、情報が探しやすくなったと感じています。さらに、各種設計情報や報告書など、構造解析データベースでは管理していなかった情報も通知できるようになり、有用な知見の共有が促進されると感じています。」
開発プロセスに「改革」を起こす、 カギとしての期待
最後に、タカノのお二方にKnowledge Explorerへの要望を伺ったところ、期待を込めて次のような回答をいただいた。
「(商品に使用する)素材を選定した際、その素材に関する過去のクレーム情報はもとより、クレームを発生させないようにするための手段や方法が出てくると良いですね。このあたり、AIなどの技術に期待しています。」(市川氏)
「我々開発の話になりますが、非常に大切であるにも関わらず、記録にもなっていない情報というのがまだまだ計り知れないくらいあって、それらが活用されず埋もれてしまっているのが一番の課題だと考えています。この課題に立ち向かうカギは、たくさんの情報や知識を如何にしてコントロールしていくかという点にあると思います。その点において、図研プリサイトのKnowledge Explorerが、今後の我々の開発プロセスに改革を起こしてくれることを非常に期待しています。」(堀木氏)