競争力のある製品を生み出す設計に欠かせない「PLM」の役割とその真価を解説!
企業が競争力のある製品を生み出すためには、設計が要になります。なぜなら、設計段階でコストも品質も多くの部分が決まってしまうからです。設計改革に向け、設計者の経験を積み重ね思考を高度化することが必要ですが、思考やナレッジはブラックボックス化していることが多く、改革も遅れがちになっています。ナレッジ共有のためには、テクノロジーを用いたデータベース化が必要となります。
また、コストを削減し、製造業において事業を正しく評価するための管理指標であるプロダクト損益管理を実現するには、設計上流の原価企画を起点としたシステムの活用や設計のデジタル化が欠かせません。つまり、PLMを活用した設計時点からの取り組みが重要になります。
この度、図研プリサイトはeBook『ERPとPLMの高度な連携で真のコンカレントエンジニアリングを実現』を作成しました。本eBookではシステムを活用した設計時点からの取り組みの重要性とそのアプローチ方法、ならびに設計から製品ライフサイクルまでのプロダクト損益管理の実現に欠かせない「PLM」の役割とその真価を解説しています。
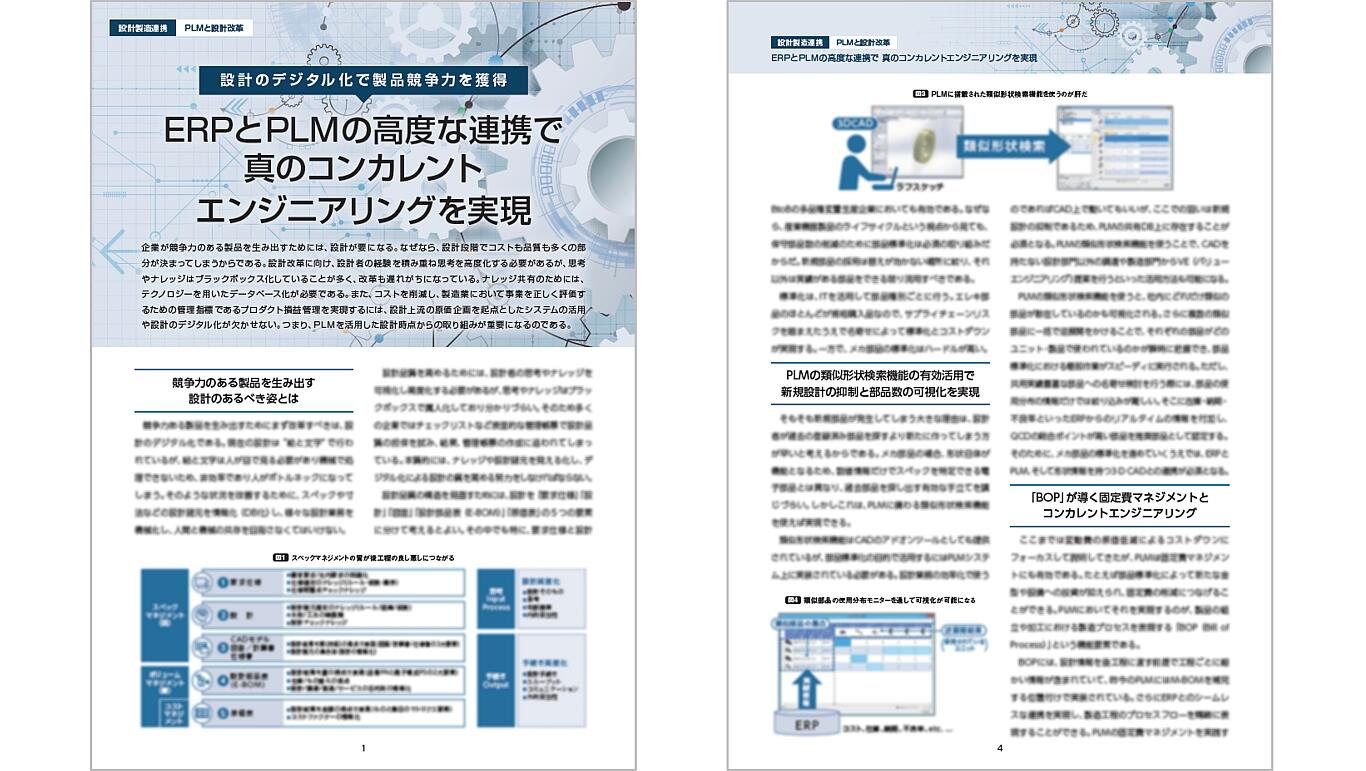
本ページでは、製品競争力を高める上でPLMが備えるべき必要な役割を、eBookから一部抜粋してご紹介します。
設計から製品ライフサイクルまでのプロダクト損益管理の実現に欠かせない存在が、PLMである。設計段階で製品コストの8割が決まると言われる中、PLMは組立型製造業の利益に直結する設計時点からの原価低減・コストダウンに役立つ。具体的にPLMを活用した設計フェーズのコストダウン手法としては、「①原価見積の高度化」と「②部品標準化の促進」という2つの取り組みがあるが、それについてはのちほど改めて紹介する。
PLMの主な役割は、BOMを中心に関連する設計情報を集約し、設計部門内で情報共有および、他部門に製品情報としてそれらを展開していくことである。それによって、設計から製造、保守までのエンジニアリングチェーンが形成される。設計段階から製造・調達・品証などの関連部門とデータを共有するコンカレントエンジニアリングを実現し、リードタイムの短縮による生産性の向上が見込める。
そしてPLMのもうひとつの役割が、コストダウンである。製造業が利益をアップさせる手段として、「値上げ」「売上数量の拡大」「原価低減」の3つが想定されるが、最も成功確率の高い選択肢が原価低減だ。組立型製造業における原価の構成要素には、部材費の占める割合が最も大きく、たとえば、売上100億円企業が部材費を5%減らすだけで億単位の利益が生み出される。製品コストを左右する設計諸元は調達や製造ではなく設計フェーズで確定されるため、上流段階からコストを意識した設計を実践することで、大きな効果を上げることが可能になる。
ただしそれを実現するためには、設計部門だけの取り組みにしてしまってはならない。設計者だけに押し付けず、設計段階から製造・調達・品証というモノづくりにかかわる全部門の知見を結集して、コンカレントエンジニアリングで設計のコストダウンを図っていく。それを可能とする仕組みを備えるのがPLMなのである。
だが、全てのPLMがこの機能を充足しているわけではない。必須要件は、設計仕掛り段階にある“生煮え状態のBOM”をストレスなく管理できることである。生煮え状態のBOMとは、E-BOMが出図構成として確定する前段階において、試行錯誤を重ねている過程のBOMのことで、本項では「Design-BOM(D-BOM)」と呼称する。市場のPLM製品には、D-BOMの管理機能を実装していないケースが多い。その理由として、「品番未採番状態にある新規部品が混在したBOMを表現できない」「CADと連携していない」という2点が挙げられる。
言い換えると、品番未確定の新規部品が混在するCADデータからシームレスに構成を取り込むと同時に、自動で仮品番を割り当てることができれば、D-BOMは表現できるということになる。そしてPLMを選定する際には、これらを簡単に行える製品を選ぶことがポイントになる。
本eBook『PLMの役割は情報集約とコストダウン』より抜粋
ウェブ掲載はここまでとなります。全文は下記eBook(PDF)にてご覧いただけます。PLMを活用した設計フェーズの具体的なコストダウン手法や、BOPによる固定費マネジメントなど、詳しい内容は是非eBookをダウンロードしてご確認ください。


