リーダー必見!コーチングで変わる部下との対話術
皆さま、こんにちは。図研プリサイトの大出です。
しばらくお休みをいただいていたこのコラムですが、このたび復活することになりました。休止期間中、過去のテーマを振り返ってみると「ビジネスになんとなく役に立ちそうなテーマ」が好評だったことがわかりました。
ただ、メルマガでも配信するコンテンツですし、あんまり堅苦しいことばかりでもな……という気もします。こんなテーマで書いてほしい!というご要望もございましたら、ぜひお聞かせください!
という導入から、「ビジネスになんとなく役に立ちそうなことがら」について思い返してみましたが、他人様に講釈垂れるような有用なスキルが見つかりません。困っていたところ、そういえば先日、社内でコーチングの研修を受けたことを思い出したので、その内容をシェアしたいと思います。今、こんなのも考えかたとしてあるんだな、というご参考になれば幸いです。
コーチングとは?
コーチングとは、相手の可能性を引き出し、自発的な成長を促すための対話手法です。もともとはスポーツの分野で使われていた概念ですが、近年ではビジネスや教育、さらには日常生活のコミュニケーションにおいても活用されるようになっています。
……と言われて、イメージが湧きますでしょうか?

私自身、せっかちな性格なので、「これどうしたらいい?」と聞かれれば「これはこう!」とパッと返してしまう性格です。
その結果、さいきん娘がなんでも「どっちか悩むけどパパ決めて!」と言うように。
それではイカンぞ娘よ!自分の人生だ、選択は自分でして、責任は自分で負わなければ!!お子様ランチのハンバーグorカレーぐらいは自分で選んでくれ!!
多かれ少なかれ、同じような経験は、仕事でも育児でも覚えがある方も多いのではないでしょうか。それ、聞く前にちょっと考えてほしいな、なんて……。(むしろ私は先輩に聞きすぎていたかな、と反省です。)
研修で特に印象的だったのは、コーチングの目的は「相手に答えを教えるのではなく、適切な質問を投げかけることで相手自身が答えを導き出せるようにする」ことだという点です。これにより、自分で考え、主体的な行動が生まれ、その結果を鑑みて改善していくという持続的な成長へとつながっていきます。
具体的にコーチングの効果として挙げられていたのは以下の4つ。
- 自発的な行動を促す:
コーチングによって、相手が自ら考え、行動する習慣が身につきます。 - コミュニケーションの質が向上する
コーチングでは傾聴や質問が重要な要素となるため、対話の質が高まります。 - 自己認識が深まる
適切な質問を受けることで、自分自身の価値観や目標を明確にできます。 - 組織のエンゲージメントが高まる
上司と部下の関係においてコーチングが活用されると、信頼関係が築かれ、組織のエンゲージメントが向上します。
ビジネスの場面では、リーダーが部下の成長を促すためにコーチングを取り入れるケースが増えています。また、教育の現場でも、生徒の考える力を養うための手法として注目されています。部下にせよ、子どもにせよ、自分で考えて自分で行動できるようになってくれたら上司として親として、嬉しいですよね!
コーチングは相手に考えさせ、自発的な気づきを促すアプローチです。答えを教えるのではなく、適切な質問を投げかけることで、相手が自ら考え、答えを見つけるプロセスを重視します。
個人的に印象的だったコーチングの特徴は以下の3つです。
- 相手の考えを引き出す
- クライアント(部下や生徒)が主体
- 正解のないものに適している(例:キャリア選択、リーダーシップ開発など)
3つ目の「正解がないものに適している」というのはコーチングを扱う上で大事なポイントと感じましたので、頭の隅に留めおいてください。
コーチングの具体的な手法
コーチングにはさまざまな手法がありますが、研修やコーチングについて調べる中で、特に有効だと感じたものを紹介します。
- GROWモデル
具体例: 部下が「営業成績を向上させたい」と話した場合、現状を分析し、達成可能な目標を設定し、それに向けたアクションプランを立てる。- Goal(目標): まず、相手が達成したい目標を明確にする。
- Reality(現状): 現在の状況や課題を整理する。
- Options(選択肢): 目標に向けた選択肢をいくつか考える。
- Will(意志): どの選択肢を選び、どう行動するか決定する。
- アクティブリスニング(積極的傾聴)
- 具体例: 部下が「最近モチベーションが下がっている」と話したら、「なぜそう感じるの?」と深掘りしながら聞き、相手の内面を引き出す。
- ポイント: 相手の話に集中し、適切なうなずきや質問を交えながら共感的に聞く。
- フィードバックの技術
- 具体例: 「このプロジェクトの進め方は素晴らしかったね。次回はもう少しスケジュール管理を意識すると、さらに良くなると思うよ。」
- ポイント: 批判ではなく、相手の行動や成果を認めつつ、改善点を伝える。
コーチングとティーチングの違い 〜主体性を引き出すアプローチ〜
とはいえ部下からすると、「どうしたらいいですか?」と上司に聞いて「どうしたらいいと思う?」なんて毎回返されていたら、それはそれで面喰らってしまいます。禅問答じゃあるまいし、聞くのがイヤになってしまいますよね。
そこで登場するのが「ティーチング」です。またカタカナが出て来たよ、なんて思いましたが、なんのことはない、われわれが一般にイメージする感じで「普通に教える」ということなのであまり難しく考えなくて良いようです。

コーチングとティーチング、どちらも人を成長させる手法ですが、そのアプローチには大きな違いがあります。
ティーチングとは?
ティーチングは、知識やスキルを体系的に伝え、相手に理解させることを目的とした指導方法です。主に学校教育や新人研修など、特定の知識や技術を効率よく学ぶ場面で活用されます。
コーチングと対比したときのティーチングの特徴は以下の通りです。
- 知識やスキルを明確に伝える
- 指導者が主体となり、教える
- 正解があるものに適している(例:数学、プログラミングなど)
コーチングとティーチングの使い分け
コーチングとティーチング、どちらの手法を使うべきか、状況によって異なります。ここで先ほどの「扱うテーマに正解があるものかどうか」という観点が生きてきます。
- 新人教育やスキル習得 → ティーチング
- 基本知識のインプットが必要な場合 → ティーチング
- 考える力を伸ばしたい場合 → コーチング
- 問題解決能力を高めたい場合 → コーチング
このように、ティーチングとコーチングはどちらか一方が優れているわけではなく、適切に使い分けることでより効果的な学習や成長を促すことができます。つまりバランスが大事というわけです。
コーチングの話を初めてきいたとき、子どもに「ナイフは右手、フォークは左手でいいの?」と聞かれ「君はどうしたい?」と聞き返す親というシチュエーションを思い浮かべ、「それはイヤだな」と思いました。
が、これは正解があることなのでティーチング、つまり「それでOK」と返してあげれば良いということですね。そこまでコーチング一辺倒でなくとも良いようです。
(利き手で力が要るほうを扱う、という根本は考えてもらったら、今後ほかのことでも役立つかもしれませんが……。夕飯食べながら7歳児に考えさせることでもないでしょう、たぶん……)
コーチングを活かすために必要なスキルとマインドセット
研修を通じて、コーチングを効果的に活用するためには特定のスキルとマインドセットが必要であることを学びました。長くなってきましたので、最後にコーチングを行う際に重要な要素を簡単に紹介します。
- 【傾聴力】
コーチングでは、相手の話をしっかりと聞くことが不可欠です。ただ聞くだけでなく、相手の言葉の背後にある意図や感情を理解しようとする姿勢が重要です。相手が安心して話せる環境を作ることで、より深い気づきを引き出せます。 - 【質問力】
コーチングの本質は、適切な質問を通じて相手の思考を促すことです。「なぜ?」と問いかけるだけではなく、「あなたはどう考えますか?」や「この経験から何を学びましたか?」といったオープンクエスチョンを活用することで、相手の内省を深めることができます。 - 【承認とフィードバック】
相手の成長を支えるためには、適切な承認とフィードバックが重要です。「よく頑張ったね」といった単純な称賛ではなく、「この部分を工夫したことが素晴らしいね」と具体的なフィードバックを行うことで、相手のモチベーションを高めることができます。 - 【信頼関係の構築」
コーチングが効果を発揮するためには、コーチとクライアントの間に信頼関係がなければなりません。誠実に向き合い、相手の価値観や目標を尊重することで、安心して意見を交わせる関係を築くことができます。 - 【成長志向】
コーチ自身も成長し続ける姿勢を持つことが重要です。コーチングは決して一方通行ではなく、コーチ自身も学び、変化していくことでより良い支援ができるようになります。
まとめ
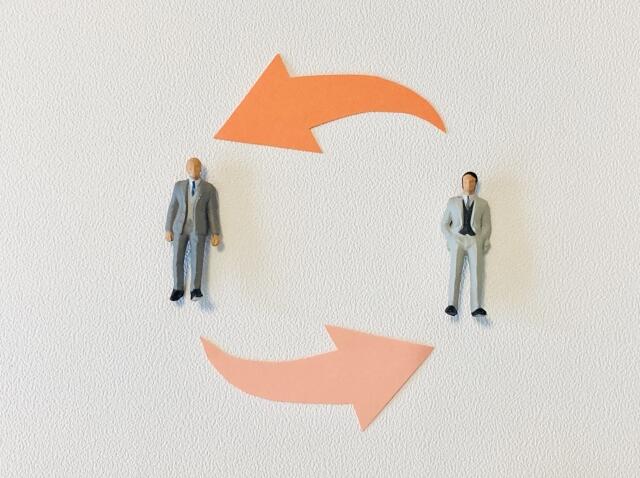
ここまでコーチングやティーチング、両者の違いなどに触れてきました。しかし個人的に、コーチングを心掛けるのに1番だいじなことは「コーチする側の心の余裕」ではないかと考えています。余裕がないと、相手の話をゆっくり聞くことってどうしても難しいですよね。
先ほどの例で言えば、「ハンバーグかカレーか、パパが決めて」「じゃあカレーな!あとから文句言うなよ!」と即答して、まくしたててはいけないのです。(反省)
4月から新しい部下が配属になる、という方も多いかと思います。いち早く業務を覚えて部署に馴染んでほしい、というのは皆さん共通の想いかと思いますが、本コラムが少しでもその役に立てば幸いです。
今回も最後までご覧いただきありがとうございました!
最後にお約束ですが、PLMシステムについて検討する機会がございましたら、ぜひ図研プリサイトのVisual BOMをよろしくお願いします!


